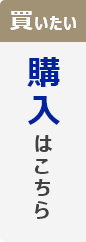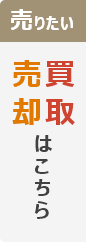カテゴリ:収益物件 / 投稿日付:2022/03/10 18:31
収益物件の資金計画~続編~

売上の基本は家賃収入
不動産投資で売上の基本となるのは家賃収入です。
その他に看板広告の収入や自販機収入、最近では太陽光収入とありますが、
不動産投資では実際には家賃収入以外ないことがほとんどです。
また、更新料も売上の一部になります。
不動産投資としての一般的な経費
不動産投資における経費は様々あります。税前キャッシュフローの計算と基本的には同様です。
・管理委託費:一般的には家賃収入の5%程度
・建物の点検・清掃費:月に2回程度、1回約1万円程度
・修繕費:家賃収入の7%程度
入退去において発生する原状回復工事、給湯器やエアコンなどの設備不具合による修理・交換
・広告費:家賃収入の5%程度
賃貸物件で退去が発生すると、賃貸募集を依頼することになります。
賃貸物件の契約が成立した時に広告費として一般的には賃料の1ヶ月分~2か月分を支払います。
1か月分であれば、家賃収入の2.5%程度になりますが、最近は2か月かかることも多くなり、
5%程度で見積もることが多くなっています。
・固定資産税・都市計画税:目安 物件価格 RC1%程度、木造0.5%程度
いわゆる「固都税」がありますが、金額は固定資産税評価額が基準となる課税標準に対して
1.7%となります。ただ、固定資産税評価は基本的には所有者でないと確認が出来ないため、
便宜上として物件価格の1%とします。
・火災保険料:家賃年収の2%程度
・減価償却費:取得時に払った建物価格を法定耐用年数により減価償却していくことで毎年の経費を計上。※毎年はキャッシュフローがでていかないことがポイント
・返済金の金利:金利分が経費 ※ただし年々少なくなる
返済金の元金部分は、経費にできない。
売上から経費を差し引いての利益を計算する
家賃収入の売上から様々な経費を差し引いた場合に、利益がいくら残るか計算してみます。
【具体例】
鉄筋コンクリート造マンション4階建、築年数17年(償却年数30年)、エレベーターなし、
物件価格1億2000万円、家賃収入1ヶ月100万円、年間1200万円(利回り10%)とし、
諸費用は自己資金で出し、融資利用フルローンでとします。
借入の条件は30年金利2%とします。この時の建物分は60%で7200万円とします。
毎月家賃収入が100万円入ることとなり、賃貸管理費や修繕費などの諸経費を家賃収入の20%と
すると差引80万円となります。ここから毎月の銀行への返済分44万円を差し引いた金額が
毎月のキャッシュフローになりますが、利益計算は違ってきます。
利益計算としては経費算入できる金額のみ差引できます(元金は経費にならない)。
基本的には支払い金利が経費として認められていますので、1ヶ月当たりの支払い金利は20万円と
なり、この金額を利益から差し引きます。
ここまでで、毎月の利益は60万円、年間利益は720万円となります。
ここから固都税120万円、火災保険料20万円を利益から差し引くと580万円です。
また、建物の減価償却費として1ヶ月あたり20万円、年間で240万円となります。
この減価償却費を上記の利益から差し引くと340万円が最終的な税引き前の利益となります。
この税前利益に、税率が20%~50%前後までかかることになります。
個人や法人によって大きく異なりますが、ざっくり30%程度で見積もっておくと良いでしょう。
個人の高額サラリーマンは、法人で取り組んだ方が良いことがわかると思います。
アパートローンの返済方式について!!
アパートローンとは賃貸アパートやマンションなどを建設、購入、またはリフォームをする費用を
借入するローンのことです。
一般的な住宅ローンなどとは違い、融資審査が厳しく、借入金利も高くなっているのが特徴です。

アパートローンの返済方式について
アパートローンの返済方法は元利均等返済と元金均等返済があります。
①元利均等返済
返済期間中の支払金額が一定となる返済方法です。
不動産投資で収益物件を購入するときには、基本はこの元利均等返済方式を選択します。
長所としては、毎月の支払金額が一定しているため、返済計画が立てやすいことです。
これが最大のポイントです。毎月の支払いが一定しているので、税前キャッシュフローの予測を
立てるのにとても有効ですし、毎月のキャッシュフローの収支が組み立てしやすいからです。
短所としては、当初の支払金のほとんどが金利となり元金分が少ないことです。
短所と呼ぶかについては、議論があるかと思いますが、当初は経費となる金利が大きいので、
キャッシュフローがとても残りやすい状態ができます。
ただ、元金が減りにくいため、すぐに売却したいと思った時には、なかなか残債が減っていないと
いうことがあります。アパートローンでの30年元利均等返済であった場合、15年経過した時に
元金は半分以上残っていることになります。
返済期間は半分になりますが、元金は思ったよりも減っていないことが多いので注意が必要です。
②元金均等返済
その名の通り支払金の元金を均等に支払っていく方法です。
毎月の支払元金は一定になりますが、当初の支払金利が多くなります。
例えば5,000万円のアパートローンを金利2%、期間20年で借入をした場合の元利均等返済と元金均等返済では、実は支払総額はそれほど変わりません。
元利均等返済:
・毎月の支払金額は最後まで変わらず252,941円で、総支払金額は60,705,899円
元金均等返済:
・最初から最後まで元金返済金額は208,333円
・金利部分は、支払金額が徐々に減る
・元金と金利を合計した返済合計金額が減る
・最初の返済金額は291,666円で最後は208,413円、総支払金額は60,041,565円
融資額5000万円、金利2%、返済期間20年で元利均等返済と元金均等返済では、
その返済総額の差額は664,334円となります。
融資額5000万円に対して1.3%程ですが、元金均等返済の方が返済額の総額は小さくなります。
ここだけを見ると、元金均等返済の方が良いかなと思う方もいますが、一番の問題は、
最初の返済金額です。元利均等返済252,941円に対し、元金均等返済291,666円になり、
4万円ほどの返済の差がでます。
月々の返済の負担が、当初大きいのが元金均等返済方式のデメリットです。
キャッシュフロー経営を目指すときには、4万円は当初大きな差に感じるでしょう。
そのため、まずは元利均等返済方式を選択しておくのが、鉄板です。
中級者以上になり、元利均等返済と元金均等返済でどちらの返済方法であっても、
支払に問題がでないようであれば、元金均等返済を選択することも検討することは有りです。
アパートローンの変動金利と固定金利について
個人の住宅ローンも投資用のアパートローンも銀行融資として借入することは同じです。
そして、その支払金利についても変動金利と固定金利の2種類があります。
固定金利の場合は、さらに全期間固定金利型と固定金利選択型の2通りがあります。
変動金利はその名の通り金利が変動する返済方法です。
基本的には4月と10月の基準金利がもととなりますが、銀行によっては毎月金利の見直しがあると
いう場合もあります。
金利が変動するとはいえ、毎月の支払金額も変動するのかというとそうではありません。
金利が変動した場合には、元金と金利の割合を調整され当初5年間の支払金額は一定になります。
支払金額は5年間の支払状況によって、最大で25%増となりますが、固定金利よりも変動金利の利率が
低いため、昨今の低金利で変動金利を選択する人も増えています。
ほとんどの銀行で変動金利から固定金利への切り替えは可能としています。
固定金利としては、全期間固定型と2年や5年など一定期間の固定型があります。
原則として、固定金利期間は金利が変動しない代わりに繰り上げ返済ができないようになります。
もし、固定金利で、繰り上げ返済する場合は、違約金が設定されているため、物件売却して返済する
場合でも違約金を忘れてはいけません。
また、通常はどの時点であっても、固定金利は変動金利よりも金利が高い設定となっています。
金融緩和が異常に行われている場合は、変動金利より固定金利が安いという逆転現象が起きる場合も
ありますが、稀だと考えてください。
通常、事業性融資であるアパート経営を考える上では、金利の一番低い変動金利を選択することを
お勧めします。固定金利は、途中で繰り上げ返済すると違約金が取られること、
金利が高いことを考えると、よほど長い期間保有することを想定しなければ、選択しない方が
ベターです。
以上、センチュリー21SEEDでした。