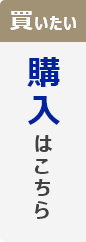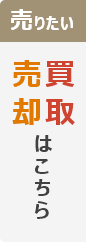カテゴリ:収益物件 / 投稿日付:2022/03/06 18:06
レントロールとは

机上でレントロールを確認するステップ
【ステップ①:収入が正しいかを確認する】
・家賃表はそもそも間違っている可能性があること
不動産業者に悪気はなくても、家賃表が間違っていることがあります。
家賃自体であったり、家賃の合計の集計であったり、そのため、家賃表をざっとみて
おかしな家賃がないかどうか、家賃の合計値をざっと暗算できるようにしておきましょう。
・家賃表には記載されていない収入があるケースがあること
代表的なのは、自販機、アンテナ収入、コインランドリーです。
これらを含めて家賃表を見る必要があります。
・水道代を収入に含めている場合がある
水道代を固定にしている場合があります。各部屋2000円等です。
そのため、水道代は収入であるのは、いいのですが、この時に支出として水道代を払う必要が
ありますので、すべてを収入にすると利回りを見誤ります。
水道代については、収入に記載されていても収入から外すか、最大でも50%分までにするのが
妥当です。
不動産業者から水道代の支出が取れるのであれば、その水道代費用を教えてもらってください。
その場合は、水道代受領分から水道代支出を引いた金額を収入としてください。
例えば、1棟マンションで1Kが28部屋あります。
各部屋から2000円受領しているので、28部屋×2000円=56000円/月が収入に計上されます。
そして、支出としては、約4万5千円~6万円/2か月のため、1か月あたり、2万2千円~3万円程度
になります。したがって、収入対比で50%前後程度になります。
【ステップ②:家賃が適正かを分析する】
・現状家賃に引き直す(昔入居している人は家賃が高い)
10年前以上に入居している方もいます。そのような方は、家賃が高いままになっています。
現在の家賃と2万、3万違う場合もあります。
現状の実力を見る上では、現在の家賃に引き直すことが必要です。
この作業を怠ると、取得後に退去ごとに利回りが低下していくことになります。
確認の方法は、Homes、Suumo、atHomeなどの大手ポータルサイトで同じ条件で
入れて確認します。
・同じ法人の複数入居の割合を確認する(同じ法人の入居率:30%以内)
法人が一括借りしているケースは、そもそも融資が難しいです。
どのくらいの割合だと危険かというと、30%以上を同じ法人が一括借りしている物件は
気を付けておいた方がいいでしょう。
なぜかというと、シングルとファミリーで若干違いますが、毎年20%程度が入れ替わると
想定してください。その入れ替えに、法人一括借りの入居者が一斉にでていくと、
50%が入れ替わり=空室募集の対象となります。
そうすると、募集が大変になり、返済に困るケースがでてきます。
返済比率50%を想定しているので、50%の空室で、返済がやっとで、その他の経費は持ち出し
になります。この水準に来ると、とても危険です。
そのため、同じ法人の複数入居は、15%程度の部屋数にしておいた方がよいでしょう。
・同じ契約年月の入居者を確認にする
学生物件の場合は、同じ契約年の学生は、同じ年度に一斉に退去することになります。
そのため、同じ契約年が40%あると、その年に40%の入れ替わりの可能性があるということに
なります。25%が望ましいですが、そのような配分には基本的にはならないので、40%程度まで
は許容せざるを得ないのが実態です。
通常の社会人、学生が混在する物件で、同じ契約年が多い場合、何かの条件をつけて一気に埋めた
跡になります。そのように無理に埋めているケースは入居から退去までのサイクルが短くなる
傾向があるので、気を付けた方がいいでしょう。
まずは、基本的なレントロールの確認事項となります。
したがって、物件概要からみて購入に値する物件と判断した場合は、
レントロールの確認を必須で行いましょう。
【ステップ③:融資が受けれる物件かどうか】
・店舗・事務所比率が30%未満であること
店舗・事務所比率が30%以上になると、個人向けのアパートローンは難しくなります。
大規模大家で実績があるなどの条件がないと、店舗・事務所比率の高い物件へのチャレンジ
は厳しいです。
登記簿謄本!!

登記簿謄本は、不動産の権利関係が記載された公的な書類となります。
これから賃貸経営者になるのであれば、基本的なことを理解しておく必要があります。
登記簿謄本とは
不動産は高額なものであり、その不動産を誰が所有しているのか、誰がその不動産に担保を
付けているのか、などが明確になっていないと、社会が混乱します。
購入したのに、違う人が、俺の土地だ!と主張してきたら大変ですよね。
したがって、不動産の権利関係を法務局にある登記簿に記録することで、権利を主張できる制度になっています。
つまり、売却により所有者が変わった場合や、新しく権利(担保)が設定された場合など、
権利関係に変化が起きたときに登記を行います。
そして、全国各地にある法務局で申請すれば、誰でも取る事ができます。
不動産登記においては、土地と建物は別々のものになります。
なぜなら、土地は地主から借りていて、建物だけ所有している場合があります。
その時は、土地の権利は地主、建物だけ自分の権利という関係になります。
したがって、土地と建物は別々の登記簿に登記されます。
どのような権利関係があるか?
どのような権利関係が記載されているかというと、不動産の権利の中で、一番わかりやすくて
身近なものといえば、「所有権」です。
収益不動産を購入すれば、売主から自分へ不動産の所有権を移します。
その所有権が移されたことを、不動産登記簿に記録することになります。
このことを、所有権移転登記といいます。
不動産の登記は、所有権だけではなく、抵当権も設定できます。
抵当権とは、銀行等が資金を融資する代わりに返済が終了するまでは、土地と建物を抵当権として
設定することになります。
つまり、返済が滞った場合には、銀行は抵当権を行使して、あなたから土地と建物を取り上げて
売却することができるようになります。
返済が終わるまでは、自分の完全なる所有ではないということです。
不動産投資で一般的に出てくるのは、所有権と抵当権です。
賃借権も登記できないことはないですが、賃貸募集して入居するたびに登記を認める大家は
いないので、賃借権の登記はないので、地上権くらいです。
地上権は、賃借権と同様に他人の土地を利用できる権利で、借地借家法の適用があります。
やや難しいので忘れても問題ありませんが、地上権と賃借権との違いは、賃借権が契約なのに対し、
地上権が所有権と同様に物権であるところです。
簡単にいえば、地上権は物権であるからほかの人に主張できますし、地主は地上権の登記に応じる
義務があります。
そのため、土地の所有者が変わっても地上権を主張して建物に住むことができるのです。
登記簿謄本と権利証は違う
登記簿謄本と権利証は別のものです。
権利証とは、登記簿謄本に権利を登記したことが完成した事を記している「登記済の証=権利証」
という関係になります。
この権利証を持っていないと次に権利を移転したり、抵当権を設定したりすることが
できなくなります。
登記簿謄本は、法務局にいけば、誰でも発行できるものですが、権利証は基本的に一度きりしか
発行されないため、権利証は大切に保管しておく必要があります。
権利証をもっていなくても、登記簿謄本が変更できると大変なことになるため、
権利証が所有権移転登記のときに必要な理由となります。
登記簿謄本・権利証により権利を主張できる
いくら、売主と買主で契約して決済しても、登記簿謄本の所有者が売主のままであったら、
買主は自分の所有であることを主張できなくなります。
そのため、決済と同時のタイミングで司法書士が、法務局に走り、所有権移転登記を行う必要が
あります。
自分の所有であることの権利をきちんと主張できるようになることが、
「登記は、第3者に対して権利を主張できる」ようになったという言い方とします。
よく宅建の問題で出てくる、「二重売買」によるケースです。
【状況】
・売主は、あなたと売買契約をいて決済したが、所有権移転登記をしていない
・あなたが所有権移転登記をしようとしている間に、売主がさらに「ほかの人」に不動産を売却し、
ほかの人が所有権移転登記を先にしてしまった。
【結果】
あなたの方が、先に不動産売買しているのにも関わらず、「ほかの人」が先に所有権移転登記を
完了してしまっているので、「ほかの人」に対してあなたは、所有権を主張できなくなります。
つまり、「ほかの人」の所有権が優先されることになります。
登記簿謄本に記載のある権利関係は、正しいものであると推定されます。
したがって、登記はとても重要な効力を持っているので、自分の権利を守るためには、
決済と同時に所有権移転登記を行う必要があります。
登記簿謄本が、第3者に権利を主張=対抗するものというのが理解できましたら、
具体的に登記簿謄本に記載されている項目がどのような内容になっているのかをある程度、
理解しておきましょう。
以上、センチュリー21SEEDでした。