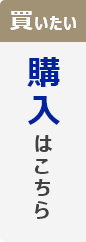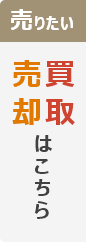カテゴリ:収益物件 / 投稿日付:2022/03/08 18:11
収益物件の融資!!

金融機関の融資期間は、建物耐用年数次第
不動産投資の醍醐味といえば、融資を活用した「レバレッジ効果」です。
金融機関から融資を受けて不動産投資をすることで、より効率的に利益を上げる事が可能になります。
そのため、不動産投資において「融資」は非常に重要なポイントとなりますが、
特に注意しなければならないのが「融資期間」です。
不動産投資において「融資期間」がなぜ重要か
不動産投資において最も注意が必要なのは「キャッシュフロー」です。
銀行融資を受けて不動産投資をする場合は、毎月常に「返済」という支出が発生します。
家賃などの収入からこの返済という支出を差し引いてもお金が残るような資金計画を立てなければ、
その不動産投資は必ず失敗してしまいます。
そして、毎月の返済金額に一番影響する要素が「融資期間」なのです。
仮に1億円を無利息で借りるとしましょう。
1億円を10年で返済するには、毎年1,000万円、毎月約83万円返済しなければなりませんが、
融資期間が30年であれば、毎年約333万円、毎月約27万円の返済になり、
格段にキャッシュフローは楽になるのです。
融資期間はどうやって決まるのか
では銀行は融資期間をどのようにして決めるのでしょうか。
結論から言うと、建物の「法定耐用年数」です。
法定耐用年数とは、物理的な寿命から導き出した「税法上の法定耐用年数」のことで、
建物の構造ごとに次のようになっています。
1:木造…22年
2:軽量鉄骨…27年
3:重量鉄骨…34年
4:鉄筋コンクリート…47年
銀行側は融資の際に、その不動産に抵当権を設定します。
そして万が一融資したお金が貸し倒れとなる恐れがある場合は、抵当権を実行してその不動産を
売却し、残りの残債務の返済に充てる事になるため、対象となる物件の法定耐用年数は融資期間を
決める上で非常に重要な要素となります。
ただし、法定耐用年数=融資期間ではなくそれよりも短い期間となるのが一般的です。
例えば新築の鉄筋コンクリートマンションだとしても、最長で30年というのが融資期間の原則と
なります。不動産投資ローンは住宅ローンとは違い、簡単には融資期間を長くしてもらえず、
また、信用が乏しい初心者投資家の場合は、融資期間を短縮されるケースもあります。
中古物件の融資期間には注意が必要!
先ほどの法定耐用年数は、あくまで建物が新築である事が前提です。
もしも中古物件に投資する際には、法定耐用年数は次のように計算します。
【法定耐用年数ー経過年数】
例えば築20年の鉄筋コンクリートマンションであれば、47年ー20年=27年が残存する
法定耐用年数となり、融資期間はその分短縮される事となります。
注意が必要なのは、ここで言う法定耐用年数は、減価償却費を計算する際の経過年数とは
別物ということです。
中古マンションの減価償却計算をする際の耐用年数は、次のような計算をします。
1:法定耐用年数を完全に経過した物件の場合
【法定耐用年数×20%=残存耐用年数】
2:法定耐用年数の一部を経過した物件の場合
【(法定耐用年数?経過年数)+(経過年数×20%)=残存耐用年数】
先ほどの例と同じ築20年の鉄筋コンクリートマンションで計算しても、
(47年ー20年)+(20年×20%)=31年
と、こちらの方が残存耐用年数が長くなります。
ただこれはあくまで減価償却計算を行なう際の残存耐用年数であって、金融機関側が融資期間の目安と
する残存耐用年数ではないため間違えないようにしましょう。
実際は残存耐用年数よりも融資期間は短くなる
このように融資期間は対象となる物件の「残存耐用年数」が一つの目安となりますが、
実際はその年数よりも融資期間は短くなる事が多くなります。
銀行側はその物件の担保価値を慎重に検討して融資期間を割り出すため、例えば土地値が高い都心部の
物件と土地値が安い地方の物件では、残耐用年数が同じだとしても、融資期間に違いが出る可能性が
あります。
要するに銀行側は、万が一の際にその物件を売却して残債務を回収できるのかどうか、
という点を重要視しているのです。
銀行が用いる経済的残存耐用年数という考え方
経済的残存耐用年数とは、先ほどの税法上の法定耐用年数とは違い、物理的劣化状況や経済状況など
総合的に勘案して、実際のところあと何年の稼働が可能なのかという観点から導き出す耐用年数の
ことをいいます。
この考え方は、融資審査が厳しい都市銀行や一部の地方銀行などで用いられており、
例えば鉄筋コンクリートであれば47年ではなく40年を法定耐用年数として、
そこから経過年数を差し引く計算をします。
例えば築年数15年の鉄筋コンクリートの場合、次のようになります。
通常:47年ー15年=32年
経済耐用年数:40年ー15年=25年
このように同じ条件でも、経済的残存耐用年数の考え方をベースにされると、融資期間が短縮されてしまうのです。
金利・融資期間による返済額!
返済シミュレーションをする時には金利や期間、元利均等返済や元金均等返済など様々な条件が
あります。
例えば、金利が高いほど、そして返済期間が長いほど返済額は増えていきます。
これら借入条件の違いが、どの程度返済額に影響してくるのかなどについて、いくつかの具体的な
条件のもと検証してみたいと思います。

比較①:元利均等返済VS元金均等返済金利2% 融資期間20年
まずは融資金額5,000万円、金利2%、融資期間が20年の条件で元利均等返済と元金均等返済の
シミュレーションをしてみましょう。
元利均等返済は毎月の返済金額が均等になる返済方法です。
支払い当初から最後の支払まで支払金額は同じになるため、最初は金利の割合が多く元金の割合が
少なくなります。
返済期間が経過していくことで徐々に金利と元金の割合が逆転していくことになります。
・元利均等返済:借入金額5,000万円、金利2%返済期間20年
支払金額:毎月252,941円
1回目の元金の返済額が169,608円、金利の支払額は83,333円となります。
金利の変動がなければ元金と金利を合わせた合計額の返済額は変わらずに、元金部分の返済額の
割合が徐々に増えていき、最後の240回目の支払いでは元金返済額253,000円、金利支払額420円と
なります。
・元金均等返済:借入金額5,000万円、金利2%返済期間20年
支払金額:初回291,666円
1回目の元金の返済額が208,333円、金利支払額は83,333円となります。最初の返済負担が大きい。
元金均等返済では元金の返済額が1回目の返済額から最後まで変わりませんが、240回目の返済は
微調整が入り208,413円になります。
この毎月の元金の返済額は変わりませんが元金の残額に金利が適用されるため、
金利の支払額が徐々に減っていきます。
比較②:融資期間 10年 VS 30年
金利2% 融資期間10年 元利 VS 金利2% 融資期間30年 元利
ここでのシミュレーションは、融資額5,000万円を元利均等返済、金利は同じ2%とし、
融資返済期間を10年と30年でシミュレーションしてみます。
・返済期間10年:毎月の返済額 460,067円
ただ、返済期間が短いため返済総額は55,208,011円となり、金利支払総額は5,208,011円と
なります。
・返済期間30年:毎月の返済額 184,809円
返済期間10年に比べると半額以下になります。ただしこの金額を30年間、360回分を返済していく
ことになります。そうなると元金と金利を合わせた返済額の総額は66,531,359円となり、
金利の支払総額は16,631,359円となります。
金利が同じであれば返済期間が短い方が金利の支払期間も短くなり、金利の支払総額も少なく
抑えることができます。
実際、融資額5,000万円、金利2%の場合で、返済期間が10年と30年では支払総額で1,000万円以上
も開きがあります。
同じ金額、金利の融資を受けるにしても返済期間が長くなると、返済額の総額はかなり大きく
なります。
返済期間を短くすることとで、融資額の返済総額を低く抑えることができますが、
毎月の返済金額が大きくなります。
ただし、不動産投資では返済金額だけでなく家賃収入に対する「返済比率」の方がより重要です。
そのため、返済総額が少なくなるからといって無理な返済計画を立てると、
返済比率が悪くなるため、余裕のある返済期間で借入れを行うよう心がけましょう。
比較③:金利1%、 4.5%
・金利1% 融資期間20年 元利 VS 金利4.5% 融資期間20年 元利
最後のシミュレーションでは、融資額5,000万円、元利均等返済、返済期間を20年とし、
金利を1%と4.5%で比較してみます。
単純に金利が高い方が金利支払額も増えるので返済総額も大きくなるのですが、
どれほどの差があるのか実際に検証してみたいと思います。
・金利が1%、返済期間20年:毎月の返済額 229,947円
この返済額が20年続くと返済総額は55,187,192円となり、その内の金利分は5,187,192円と
なります。
・金利4.5% 返済期間20年:毎月の返済額 316,324円
20年間の返済額総額は75,917,926円となり、その内金利の支払総額は25,917,926円となります。
金利が4.5%では金利1%と比較すると毎月の返済額の差額は86,377円となり、
総支払額の差額は20,730,634円となります。
金利4.5%では元金の1.5倍以上を返済することになり、金利が3.5%違うとかなりの差が
出ることが分かります。
信用情報の確認!
不動産投資を始める際には、あなたが融資を受けられるかどうかは、あなた自身の「信用情報」
にかかってきます。
銀行は融資の申込みがあると、その人に融資できるのか、融資できるとしてその金額はいくらまで
なのかを審査します。
この審査をする際に金融機関が確認している情報を「信用情報」と言います。

信用情報ってなに
ではそもそも信用情報とは、具体的になんなのでしょうか。
例えば皆さんは「ブラックリスト」という言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。
ブラックリストとは、一般的には「クレジットカードの返済を滞納したり、自己破産などの債務整理を
すると、そのリストに名前が載る」というようなイメージかと思います。
ただ、実際には「ブラックリスト」というリストは公式には存在していません。
皆さんがブラックリストと呼んでいる情報とは、指定信用情報機関が扱う「信用情報」の中の
ネガティブな情報のみを指しているのです。
指定信用情報機関とは、加盟している金融機関やクレジットカード会社などから「信用情報」を
収集しデータベース化し、金融機関からローンの申し込みをしてきた人の信用情報の照会があった際
に、その人の信用情報を回答しているのです。
指定信用情報機関に登録されている信用情報には、以下のようなものがあります。
【信用情報の具体例】
1:個人の属性
申込書に記載されている氏名や生年月日などの基本情報
2:既存の契約内容
既存利用しているクレジットカードやローンの契約内容、商品名、支払回数、極度額など
3:支払状況
過去の入金履歴や延滞情報、自己破産に関する情報などで、ここでいうところの延滞情報が皆さん
の呼んでいる「ブラックリスト」に該当する情報となります。
4:借金残高
年間請求予定額や遅延の有無など
金融機関は、これら登録されている信用情報に基づいて、その人に支払い能力があるのかどうかを
見極めて、融資の是非を判断しているのです。
分かりやすく言うと、今現在あなたにいくらの借金があって、その返済状況はどうなのかが丸裸に
なってしまうということなのです。
融資を受けるために超えなければならない「2つのハードル」とは
金融機関から融資を受けるためには、次の2つのハードルを超えなければなりません。
ハードル1:借金残高
まずポイントとなるのは、既存の借金残高です。
これは、不動産投資のために融資を受けているものだけではなく、住宅ローンやマイカーローン、
更にはクレジットカードの利用残高など、指定信用情報機関に加盟しているあらゆる金融機関からの
借入金額を総合して審査されます。
融資審査の申込書にも、現状の借入残高や借入先を記入する箇所がありますが、
ここにウソ偽りを書いてもすぐにバレるのは、この信用情報に照会をかけているからなのです。
現状の収入に対して、新たな借入が難しいと判断されてしまうと、融資は難しくなるでしょう。
ちなみに、借入可能な総額の目安としては、住宅ローンでいえば、年収の7~9倍程度と
言われています。
不動産投資で1億や2億の借入残高があると、銀行融資でよく言われる
「不動産投資のスピードが早すぎる」、「数年の決算書を待ってから判断したい」
と言われるようになります。
決算書で3期くらいきちんと運営していかないと、次の融資がなかなかでないことがあります。
ハードル2:支払状況
借金残高に無理のない事が分かったら、次のハードルは既存の支払い状況です。
皆さんも人にお金を貸す時は、期日通りに返してくれる人じゃなければ貸したくないですよね。
金融機関もそれと同じで、過去に返済が滞っているような人にはなるべく貸したくありません。
信用情報には、過去の借金が滞りなく返済されているのかどうかが記録されているため、
万が一滞納履歴(いわゆるブラックリストの状態)があると、融資は非常に難しくなります。
そのため、不動産投資家を目指すのであれば、クレジットカードやキャッシングの返済は、
滞りなく行なうよう日頃から心がける事が大切です。
電気、ガス、水道などの公共料金の滞納については信用情報の対象外ですが、これらの支払いを
クレジットカードで決済している場合は、滞納情報として記録されてしまうため注意しましょう。
ブラックリストに載った場合、その情報は消せるか
万が一過去にクレジットカードの支払いで延滞した経験があると、
絶対に融資が受けられなくなるのかというと、決してそういうわけではありません。
あくまで融資の際の一つの判断材料ですので、どの程度延滞したのかなど、具体的な滞納状況も
踏まえて審査されますので、必ずしもそれで審査NGというわけではありません。
なお、万が一ブラックリストとしてネガティブな情報が記録されてしまったら、どうすれば良い
のでしょうか。
これらの信用情報は、その金融機関との契約期間中については記録され続けますので、
こちらからお願いして消す事はできません。
但し、その金融機関との契約が終了して5年が経過すれば保有期間が終わるため、
登録されている信用情報は消えます。
自分の信用情報を事前に確認しましょう
信用情報の開示については比較的簡単で、ネット上からでも開示請求が可能です。
金融機関によって加盟している信用情報機関が異なります。
日本における指定信用情報機関は、以下の通りです。
1:全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)(銀行系)
2:株式会社シー・アイ・シー(略称「CIC」)(クレジット系)
3:株式会社日本信用情報機構(JICC)(消費者金融、商工ローン系)
ここでまずは融資の審査を出す前に、どのような情報が記録されているのかを自分自身でも
確認してみましょう。
以上、センチュリー21SEEDでした。